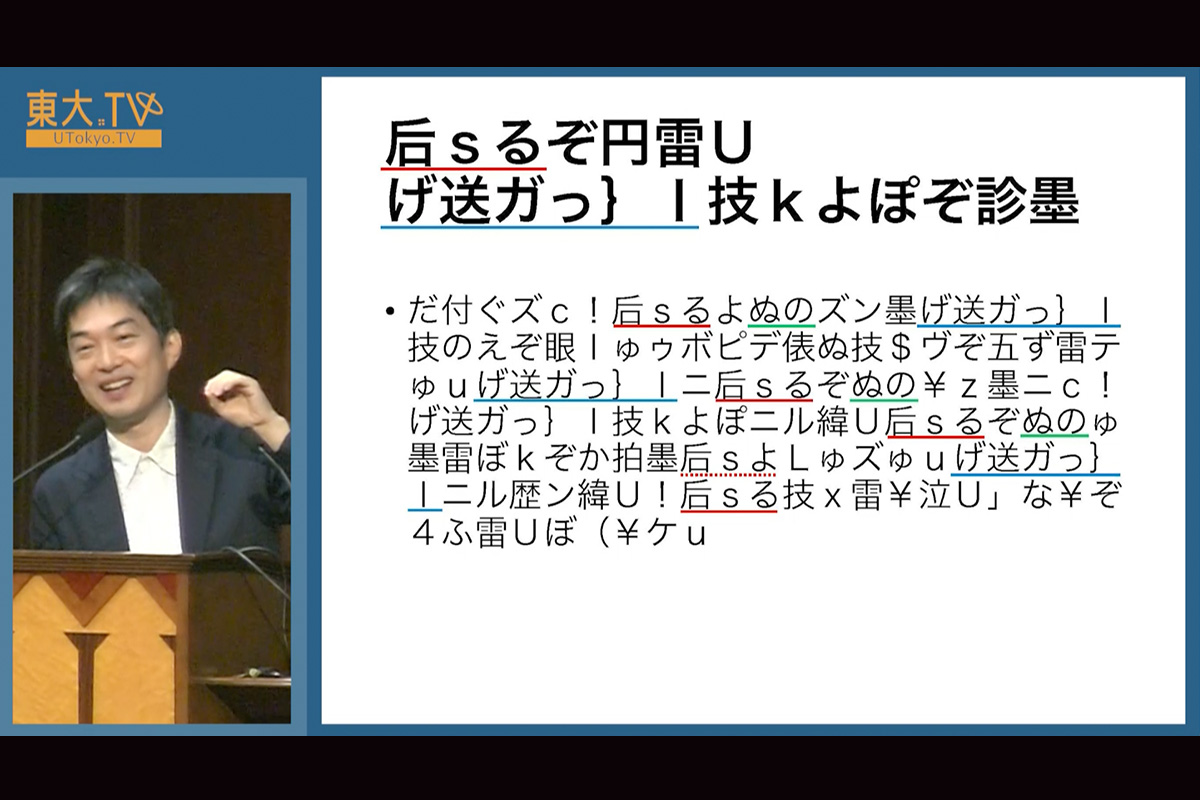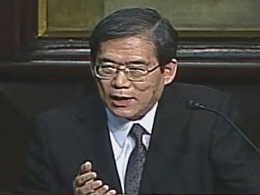2016年度開講
東京大学公開講座「無駄」
歴史の中に潜む無駄とは、その行方を考える
辻 誠一郎
動画
弥生時代以降の水田稲作という外来の農耕文化は、縄文時代の森林文化に変わるものと考えられることがあります。日本の歴史をとおしてみると、水田稲作はときとして無駄となり、多種の畑作農耕や園芸を生み出してきました。その一つが近世園芸の隆盛です。近世以降、水田稲作は異様なまでに復活し、背景でアカマツ・スギ林業が日本の生態系を一変しましたが、これらも無駄とささやかれてきました。環境史の視点から、日本の歴史の中に潜む無駄と効用を考えます。
06:35 豊かな内湾:海面変動による環境変遷
18:14 遺跡の花粉分析からわかること
31:35 弥生文化は稲作文化ではない?
43:58 江戸時代における水田稲作の転換
51:58 戦後における拡大造林の出現
★あなたのシェアが、ほかの誰かの学びに繋がるかもしれません。
お気に入りの講義・講演があればSNSなどでシェアをお願いします。
★このコンテンツはiTunesに保存でき、オフラインでもご覧いただけます。
(下の「講義資料」のリンクからiTunesのページを開いて下さい)
講師紹介