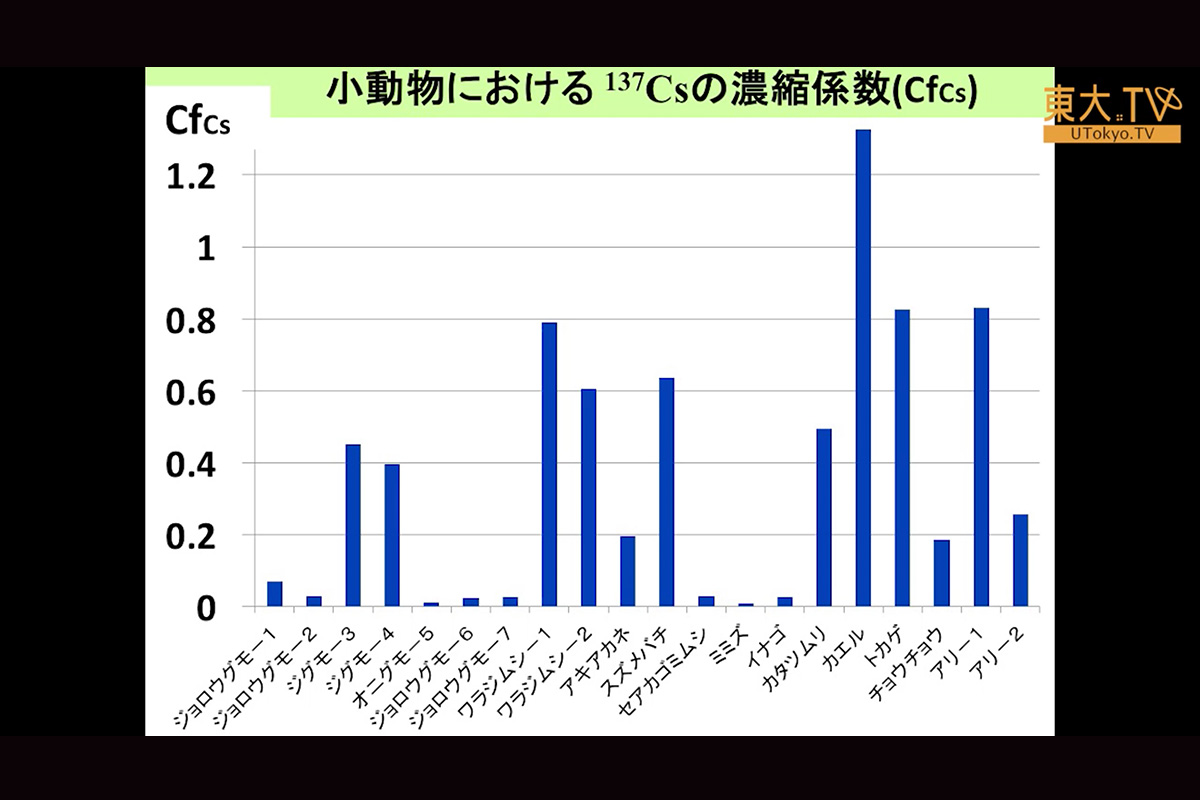2010年度開講
西垣通 最終講義「ラ・マンチャの情報学者」
最終講義「ラ・マンチャの情報学者」
西垣 通
動画
西垣通 東京大学最終講義「ラ・マンチャの情報学者」
2013年3月6日,東京大学情報学環・福武ホール(福武ラーニングシアター)にて。
講義資料(講義録について)
「本稿は、東京大学大学院情報学環・学際情報学府教授であった西垣通の最終講義の記録である。この講義は、同教授の 2013 年 3 月末の定年退任にともない、同年 3 月 6 日に東京大学福武ラーニングシアターにておこなわれた。内容はおもに情報学環の教職員や学生に向けたものであるが、一般にも公開された。わかりやすくするため、本講義録では当日話した内容を多少補ったり言いかえたりしている部分もある。」
講師紹介