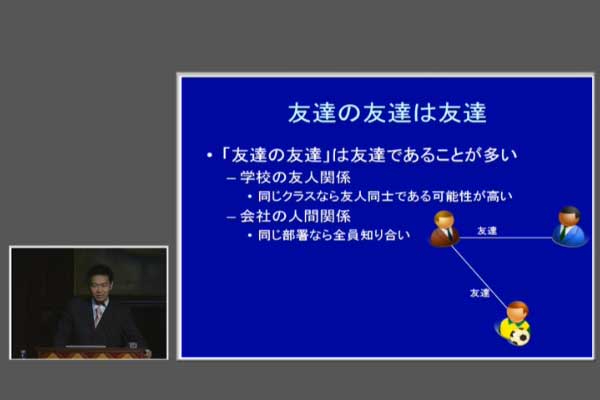2011年度開講
東京大学公開講座「だます」
偽薬・プラセボ
津谷 喜一郎
動画
Placeboは日本では一般に「偽薬」と訳されます。もともとラテン語訳の聖書にでてくることば で「喜ばせる」というポジティブな意味を持ちます。どうして日本では「プラセボに過ぎない」な どとネガティブな意味合いで使われることが多いのでしょうか?その語源、漢字文化圏での類似の 用語、臨床試験でのプラセボの作成法、臨床試験と診療での使われ方の違い、倫理との関係など、 プラセボの多義的性格を探ります。
このコンテンツは、iTunesに保存してiPhoneやiPadからいつでもご覧いただけます。
(上記をクリックすると新しいウィンドウが開き、Apple社のページを表示します。)
★東大TVのコンテンツがほかの誰かの学びに繋がるかもしれません。
あなたのお気に入りの講義・講演があれば、動画の上にあるSNSボタンからシェアをお願いします。
講師紹介