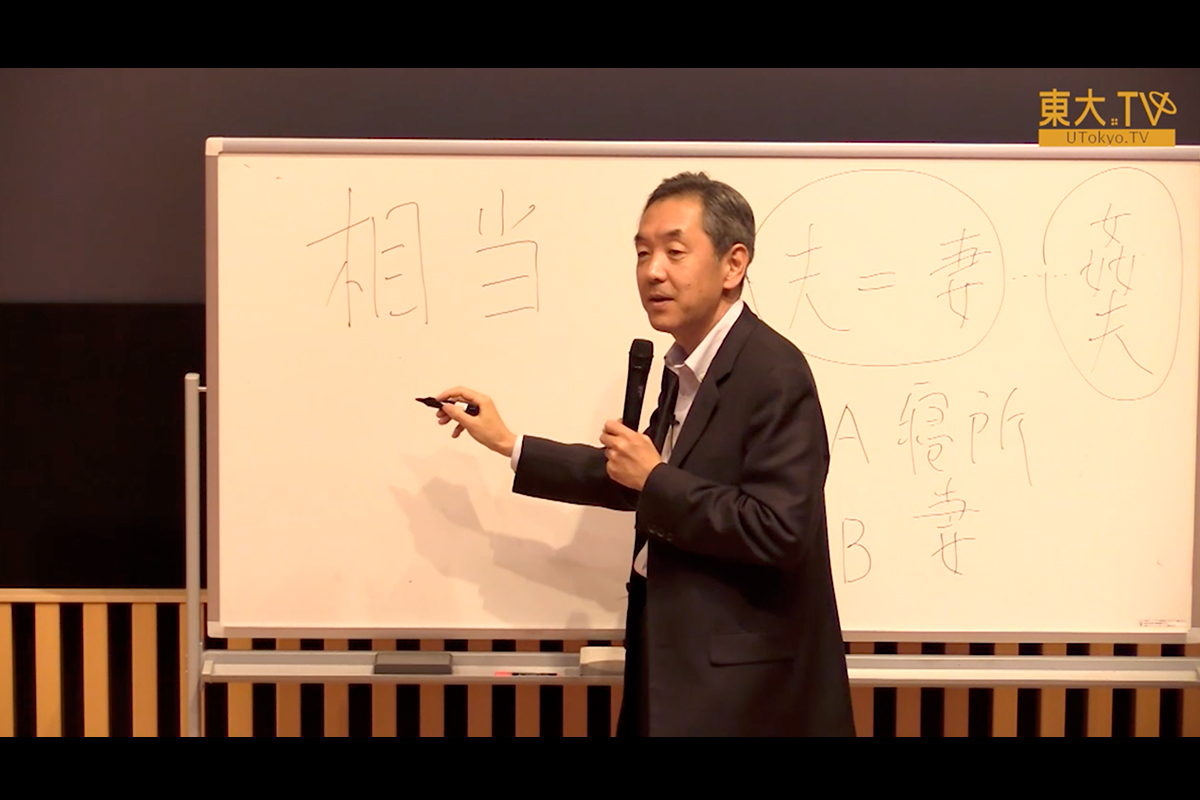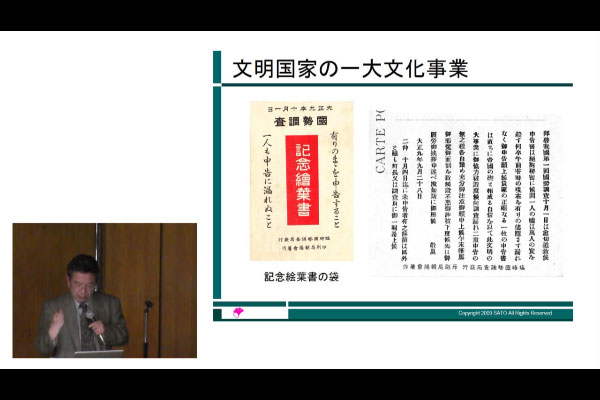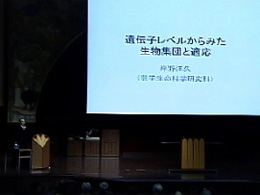東京大学公開講座「水」
動画
太陽系の第三惑星―地球―。もし、地球に水が存在しなかったら・・・。海は無く、原始生命も発生せず、水循環に代表される生命圏と地球圏との物質循環も起きなかったはずです。したがって、人類が進化することもなく、その活動の基盤となった地球環境も形成されなかったでしょう。人類は今や生命圏の枠を越えて、人工物を含む人間圏ともいうべき世界を生み出すに至りましたが、私たちが直面している地球環境問題はこの人間圏と地球圏の間に持続可能な物質循環の道筋をつけることと言ってもよいでしょう。古代ギリシャの七賢人の一人であり、最初の自然哲学者とされるターレスは「万物の根源は水である」という有名な言葉を残しました。二千数百年の歴史を経た現在、私たちがこの言葉の持つ意味を考えるのは大変意味のあることだと思います。
水は酸素と水素から構成される簡単な構造をしていますが、その化学的性質は複雑であり、効果的な溶媒として地球圏においても生命圏においても極めてユニークな役割を果たしています。水の科学は理学的にも工学的にも最先端をゆくトピックです。生命体の維持に不可欠な水は、当然、人が生きるためにも不可欠です。安全な水の確保と健康の維持の問題は私たちが抱える最も身近なテーマであるといえるでしょう。一方で、水の確保は国内においても国際社会においても紛争の原因になってきました。水と政治・経済という視点から歴史、人間関係、国際関係を考えるのは極めて今日的な問題です。社会・経済活動の中でも農業は水循環変動の影響を最も受けやすい分野ですが、この水循環変動の原因となる気候変動に適応するための科学技術は、地球温暖化の進行に伴って、ますますその必要性が高まっています。地球は水惑星とも呼ばれますが、それは潜熱の吸収、放出を伴いながら、水が気相、液相、固相の間を自在に行き来できる惑星条件下にあるからです。水蒸気となり、雲となり、雨となり、時には氷となって岩を砕き、川となり、海に流れ込む水。時に穏やかで、時に荒れ狂う水の諸相とそれが織りなす風景の下で世界各地にユニークな社会と文化が育くまれてきました。
本講座では様々な視点から水を対象とした最先端の研究を集約し、総合的に水の文化と科学を考えてみたいと思います。